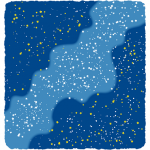7月に近付くと街のあちこちで七夕の飾りつけをよく見かけるようになりますね。
小さな子がいる家庭では、笹を用意して、短冊にお願い事をしたり、折り紙などで飾りつけをしたりします。
子供のころからの毎年の行事なのに実は私自身、七夕がなんなのか、あまりよくわかっていませんでした。
そこで七夕について、少しまとめてみました!
七夕の由来について
そもそもなんで「七夕」が「たなばた」?
あらためて考えてみるとさっぱりわかりません!
そこで調べてみると、
なんと「七夕」は「しちせき」だったのです!!
そんなこと、いきなり言われても戸惑ってしまいます。
では「しちせき」って何?ってなりますよね。
これは昔中国から日本に入ってきた節句の一つなんです。
節句とは年中行事を行う、季節の節目の日で、
よく耳にするものでは、「桃の節句」「端午の節句」というのがありますよね。
「七夕=しちせき」とはこの節句の仲間だったんです。
この仲間を五節句といいます。
五節句はこちら
1月7日 人日(じんじつ)
3月3日 上巳(じょうし)
5月5日 端午(たんご)
7月7日 七夕(しちせき)
9月9日 重陽(ちょうよう)
この七夕が中国から日本に伝わり日本の棚機つ女(たなばたつめ)という行事が合わさったものという説があります。
七夕の短冊の由来について
七夕にはつきものの短冊。 これに願いを書いて飾る風習は江戸時代から始まったようです。
もともとは書道などの上達を願って和歌を短冊に書いていました。
これが江戸時代になって、習い事が上達するのを願って短冊を飾るようになることが一般に定着したようです。
短冊はカラフルな見た目で、「五色の短冊」って七夕の歌にも出てきますが、この短冊の色は青・赤・黄・白・黒の五色からなります。
これは五行説と呼ばれる自然哲学の考えからきているようです。
青(緑) 木行 樹木の成長や発育する様子から春の象徴
「仁」徳を積む・人間力を高める
赤 火行 火のような性質から夏の象徴
「礼」両親や祖先への感謝
黄 土行 植物の芽が地中から発芽する様子
「信」信じること、知人や友人を大切にする
白 金行 土の中の金属から収獲の季節 秋の象徴
「義」義務や決まりを守る
黒 水行 泉から湧き出る水から冬の象徴
「智」学業などの向上
ただし、黒には縁起が良くないと思われることもあり、あまり好まれないことから高貴な色である紫が黒の代わりに使われるようになります。
笹には生命力が強く、邪気を払ってくれるという意味があるようです。
天に向かって真っすぐ伸びてゆくので、願いを届けてくれるという思いがあったようです。
七夕飾りの由来について
七夕飾りには短冊のほかに、提灯や巾着などの飾りも笹に飾りますよね。
これらにもそれぞれ意味があります。
紙衣:一番上に飾ります。裁縫が上達しますように、着るものに困りませんように
また、災いなど身代わりになってもらう意味もあるようです。
提灯:願い事が書かれている短冊を照らします、心を明るく照らしてくれますように
巾着:昔のお財布ですね。商売が繁盛しますように、お金がたまりますように
投網:豊漁や豊作になりますように
屑籠:飾りででた紙くずを入れて飾ります。節約、ものを粗末にしないように
折鶴:長生きできますように
吹き流し:機織り、裁縫など習い事が上達しますように
など、それぞれ飾りに願いが込められています。
全く意識しないで折り紙などで作っていましたが、こんな意味があったのですね。
まとめ
七夕の短冊や飾りにもそれぞれ意味があり、さまざまな願いが込められていたようです。
その意味を知ってから短冊や飾りつけをすると、いままでとは違った気持ちになれますね。